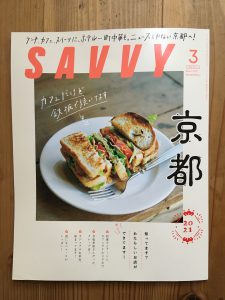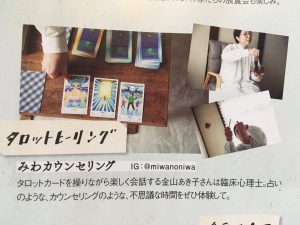さてさて・・・前回の<マインドフルネス>に続き、
今回は、セルフ・コンパッションの残りの2つの要素、<自分への優しさ>と、<共通の人間性>についてです。
<自分へのやさしさ>
セルフ・コンパッションを学んで、私自身の一番大きな学びになったのは、「自分へのやさしさ」という視点です。
私たちは、自分が苦しい時、悲しみ・怒り・恥など、否定的な感情があるときにこそ、「優しさ」を必要としています。
でも、その優しさを、苦しい時に自分に向けることは、なかなか難しいものです。
そこで、<自分への優しさを向けるワーク>の一つでは、自分が今まさに、「苦しんでいる」ことに気づいた時、
<もし、その苦しんでいるのが、自分の「親しい友達」だったとしたら、
どんな風に声をかけるだろうか?>
と、少し客観的に考えてみることをしてみます。
例えば、子育てで、子どもに対して、イライラしてしまう時を例にしてみると・・。
いつもだったら、「こんなにイライラしている。私はだめな母親だ。・・」
など、批判的な考えや、否定的な感情に、占められてゆくかもしれません。
でも、そこでまずは、「マインドフルネス」を使い、
「いま、イライラしている。・・あ、胸のあたりが緊張しているな」と
今の「苦しみ」に、「あるがまま」に気づいてみます。
そこから、「もし、このイライラしているのが、自分の友人だったら、どういう風に声をかけてあげるだろうか?」
と、少し想像してみます。
友人へだったら・・「そりゃあ、イライラもするよね。・・今日は1日、幼稚園もお休みで
ずっと子どものお世話をしてたもんね。
本当におつかれさん。どんなお母さんでも、イライラしてしまうこと、あるよー。」・・
と、声をかけてあげるかな、と思うとします。
すると今度はその声を、自分へ、少し向けてあげるのです。
そして、必要であれば、自分へ、やさしくハグ(両腕で抱きしめる動作)することや、
タッチ(胸の中心に手をあてるなど、心地よい部分に触れること)をしてみます。
不思議なことに、「あるがまま」に気づき、「友人へ」の視点から優しさを向ける事で、
「苦しみ」の体験の「質」が、変わってくることに、気づかれることも多いでしょう。
私自身、このやり方で、日常生活の中で、何度救われてきたことかわかりません。(とくに子育てで。笑)
もしも、「友人へ」の言葉を何も思いつかない時は、ただ、今「苦しみ」に気づいていることへ、
なんとなく「優しい気持ち」をむけてみるだけでも十分です。
「・・イライラしているんだね。・・(できそうであれば、自分へ心地よい範囲で、ハグしたり、触れてみる。)」という風に。
または、誰か他の「温かい人、優しい人、信頼している人を想像してみることも良いでしょう。
実在の人でも、空想上の人物などでもかまいません。
「その人だったら、この苦しみへ、どんな言葉をかけてあげるだろう?」と想像してみます。
(例えば、ムーミンママだったら・・
「まあ、イライラしてるのね。だいじょうぶ。だいじょうぶ。深呼吸して。お茶を入れましょうね。
ちょっと少し自分の好きなことをする時間をもつのもいいじゃない。」と言ってくれるかも。
そして、やさしくハグと、マッサージをしてくれるはず。(自分をハグしてみる)・・など。)
この、<自分へ優しさを向ける>プロセスは、
心とからだの状態=神経系を、<思いやり・つながりの神経回路>と言われる、
自分とのつながり、他者とのつながりを、落ち着いて持つことができる、
心身の「あり方」へと、私たちを少しずつ、連れて行ってくれるのです。
そのとき、私たちはもう、決してひとりぼっちではありません。
この「マインドフルな意識」・「ケアをする(思いやる)意識」は、
思い出しさえすれば、24時間いつもいつだって、私たちと一緒なのですから。

<共通の人間性>
「苦しみ」の体験において、人はとくに、「ひとりぼっち」や、「孤独である」と感じられやすいものです。
<セルフコンパッション>のプロセスを踏むことは、
私たちを、「孤独」な状態から、「健全なつながり」の状態へと導いてくれます。
マインドフルな気づきを持って、まずは苦しんでいる「自分自身」とつながること。そしてさらに、
少しずつ「自分へ優しさを向ける」ことで、神経回路そのものが、
自分や、他者とも落ち着いて「つながることができる」心身の状態へ、と移行してくれます。
そして近年の研究では、脳・神経回路には可塑性(変化できる力)があり、この「思いやりの神経回路」は、
大人になってからでも、いつからでも、徐々に作っていけることがわかってきています。
これも、私たちの大きな希望です。
チベットの僧であるダライ・ラマは、こんなふうに言っています。
「すべての人間は、苦しみをなくして、幸せを得たいと望んでいる。」
個々人によって、人生における「苦しみ」の状態や種類は、それぞれに違っていますが、
「痛み」や「苦しみをもつこと」は、肉体をもつ人間にとって、共通の体験です。
そして、全ての人が、そこから「幸せ」や、「健全なつながり」を求め、願っています。
その意味で、苦しみを感じるとき、実はいつだって、私たちは、ひとりではないのです。
セルフコンパッションにおける3つ目の要素、<共通の人間性>とは、
私たち人間というものが、<苦しみをもつ>ということにおいて、「つながっている」ということを、
思い出させてくれます。
人間という存在自体が、<苦しみを持っている>ということを思い出し、
そこへ少しばかりの<やさしさ>の目線を向けはじめた時、私たちの内側で、何かが変わります。
そして、その変化は、かならず外の世界へと波及してゆくことでしょう。
自分へ優しくするということは、世界へも優しくすることに等しくなっていきます。
私自身、このことを思い出しながら、自分へのまなざしを、やさしく、強く
(そのやさしさは、必要のある時には、外へ、強く主張してゆくことを含みます。)
してゆくことを、続けていきたいと思っています。
<セルフコンパッションのプロセスの、簡単なまとめ>
(初めは、あまり大きくない「苦しみ」からはじめてみます。
すべてのプロセスにおいて、「無理なく、少しずつ」するのがポイントです。)
①マインドフルネス
・今の「苦しみ」に、あるがままに気づく。
・・・「いま、苦しいね。」「今、つらい状況だよね。」と、苦しみに気づく。
・それは、身体のどこに感じられる?・・「胃のあたりが、少ししめつけられるみたい」。
・その感情に、そっと名前をつける。・・「これは、悲しみ」「これは、怒り」。
②人間の共通性
「苦しみ」は、人生の一部で、「あなたはひとりじゃないよ」と、思い出してあげる。
③自分へのやさしさを向ける。
・いま、「苦しみ」がある、と「気づいている」こと自体が、自分への優しさへの一歩。
・「この苦しんでいるのが、もし、親しい友人だったら、何と言ってあげる?」と想像し、その言葉を自分へかけてみる。
・「自分にやさしくできますように」「あるがままの自分で、いれますように」など、やさしい言葉をかけてみる。
・「今、何が必要?」と自分の「ニーズ」を聞いてみる。・・深呼吸したい、あったかいお風呂に入りたい、
少しの間一人になりたい、友人と話したい、など・・ → できる範囲で、そのニーズを叶えてあげましょう。
・自分へハグをしたり、やさしく触れてみる。
(心地よく触れる事で、オキシトシンという「幸せを感じるホルモン」が分泌されますし、
「つながりの神経」のあり方に、居やすくなります。)